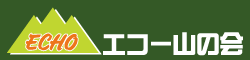| コメント |
東武東上線のみずほ台駅で、東京および浦和在住の参加者と合流し、総勢7名で出発した。30分ほどで水子貝塚公園に着いた。水子とは「水のある場所」という意味だそうである。芝生の広場には、復元された縄文時代の堅穴式住居が数個立ち並んでいる。ここにはほぼ環状に配置された、30を超える堅穴式住居跡が見つかっている。また弥生時代、さらに時代が下って平安時代の遺物も見つかっており、現在まで連綿として人が棲んでいたようである。つまり彼らにとって、この場所が暮らしやすい土地であったことを示している。もちろん当時は電気もガスもない生活で、食料(木の実や、魚獣など)は自然に依存し、十分に手に入らなかったことも多かったはずである。しかし、縄文人の暮らしは意外に豊かで充実していたかもしれないと思った。水子貝塚は、現在は高台にあるが、当時(数千年前)は台地の麓まで海がせまっていて、縄文人は貝(シジミやハマグリ)や魚などの海の恩恵を受けていた。ここは資料館が整備され、ボランティアの市民学芸員がていねいに説明してくれたのがよかった。 資料室を出て、道路の反対側の真言宗大應寺と水宮神社を訪れた。ちょうど七五三で、晴れ着のお参りの親子がたくさんいた。台地の坂道を下り、橋を渡って新河岸川の堤防に出て上流に向かって歩いた。国道富士見・川越線にぶつかり、横切って2キロほど歩くと難波田城公園である。入口を入ると、数棟の古民家が迎えてくれる。いずれも築百数十年の歴史ある、この地域の豪農の屋敷を移築したものである。古民家の庭のテーブルで昼食を摂った。難波田城は、三重の水堀をめぐらした中世の平城である。鎌倉時代から戦国時代にかけてこの地域で活躍した武将「難波田氏」の居城だった。水堀にはハスや菖蒲が植えられていて、梅雨の時期は美しいだろうと思った。難波田城公園を出て1時間ほど歩くと富士見市役所で、そこからバスで鶴瀬駅に戻り、解散した。今回の山行は、数千年前の縄文人の息吹と、数百年前の武将の盛衰にふれた山行でした。 |